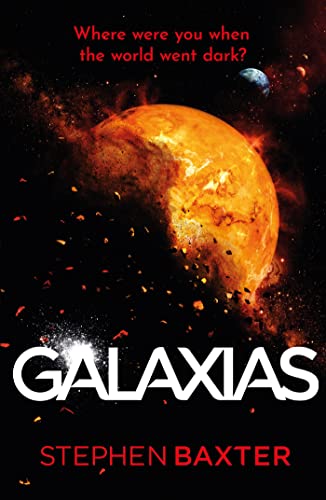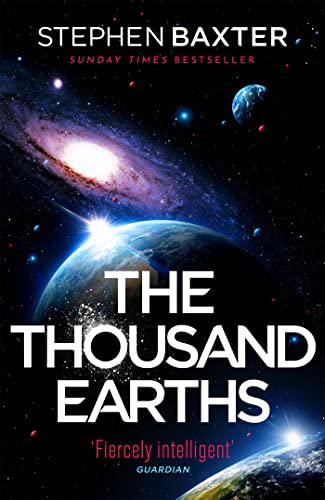現在絶賛公開中のアニメ映画『劇場版少女☆歌劇レヴュースタァライト 』
VIDEO www.youtube.com
では、物語のキーワードとして「ワイルドスクリーンバロック 」 というものが多用されています。
「ワイルドスクリーンバロック 」の元ネタは、おそらくSFのサブジ ャンル「ワイドスクリーンバロック 」 でしょう。
この記事では「ワイドスクリーンバロック 」とは何かをサーベイ して、はたして『劇場版少女☆歌劇レヴュースタァライト 』が「ワイドスクリーンバロック 」なのかを考えたいと思います。
【簡単な要約】:「ワイドスクリーンバロック 」のもともとの意味は規模が大きくてハチャメチャなスペースオペラ くらいの意味合いだったが、日本に輸出されたことで意味合いが変わりアイデア がすごくたくさん出てくるSFくらいの意味になった。『劇場版レヴュスタ』は前者の意味合いには当てはまらないが後者には当てはまるかもしれない。
はじめて、「ワイドスクリーンバロック 」(Wide-screen baroque)という言葉が使われたのは、1964年でした。
この用語の考案者は、イギリスのSF作家・SF評論家のブライアン・オールディス (1925~2017)。アメリ カのSF作家、チャールズ・L・ハーネス(1915~2005)が書いた長編小説『パラドックス ・メン』を称賛するために、その序文に自らの造語として書いたのでした。
つまり、「ワイドスクリーンバロック 」とは、もともとは『パラドックス ・メン』という特定の作品を言い表すために作られた用語だったのですね。
翻訳版訳者あとがきからの孫引き引用になりますが、そのオールディスの文章は以下のようなものとなります。
こうした純粋なSFは、ワイドスクリーン・バロック としてカテゴライズできるかもしれない。プロットは精妙で、たいてい途方もない。登場人物は名前が短く、寿命も短い。可能なことと同じくらいやすやすと不可能なことをやってのける。それらはバロック の辞書的な定義にしたがう。つまり、すばらしい文体(スタイル)よりはむしろ大胆で生き生きとした文体をそなえ、風変わりで、ときにはやり過ぎなところまで爛熟する。ワイドスクリーン を好み、宇宙旅行 と、できれば時間旅行を小道具としてそなえており、舞台として、すくなくとも太陽系ひとつくらいは丸ごと使う。(『パラドックス ・メン』p333より引用、中村融 訳)
のちに、オールディスは著書『十億年の宴』(1973年刊行)に次のようなことを書いています。
私自身の好みは、ハーネスの『パラドックス ・メン』である。この長編は、十億年の宴のクライマックスと見なしうるかもしれない。それは時間と空間を手玉に取り、気の狂ったスズメバチ のようにブンブン飛び回る。機知に富み、深遠であると同時に軽薄なこの小説は、模倣者の大軍がとうてい模倣できないほど手ごわい代物であることを実証した。この長編のイギリス版に寄せた序文で、私はそれは《ワイド・スクリーン・バロック 》と呼んだ。これとおなじカテゴリーに属する小説には、E・E・スミス 、A・E・ヴァン・ヴォークト 、そしておそらくはアルフレ ッド・ベスタ―の作品が挙げられよう。(『十億年の宴』p305~306より、浅倉久志 訳)
オールディスが挙げた作家は以下の三人です。
E・E・スミス (1890~1965)は〈レンズマン 〉シリーズ・〈スカイラーク〉シリーズで恒星規模の破壊をやすやすとこなす宇宙戦争 など、これまでとは桁違いの規模のSFを作り出しました。
A・E・ヴァン・ヴォークト (1912~2000)は、『非Aの世界』『非Aの傀儡』で、当時流行していた哲学思想「一般意味論」を応用したスーパーヒーローを描きました。そのヒーローは「一般意味論」を使うことによって超能力に目覚め、銀河系規模の陰謀から地球を救うために戦うことになります。
アルフレ ッド・ベスタ―(1913~1987)は、『分解された男(破壊された男)』にて、他者の心を読むテレパス 能力者が出現したことにより、犯罪が不可能になった未来社 会を描きました。『虎よ、虎よ!』では、全人類がテレポーテーション能力を取得したことによって、太陽系の隅々にまで一瞬でいけるようになった未来社 会を描きました。『コンピュータ・コネクション』では、宇宙のかなたから帰還して両性具有となった元宇宙飛行士の超人類を支援するために天才博士と一体化した神のごときコンピュータが出現しますが、不死のネアンデルタール人 に殴られて壊されます。
上記の作家を見る限り、オールディスが「ワイドスクリーンバロック 」という言葉で表したのは、「スペースオペラ (宇宙冒険・宇宙戦争 などをテーマにしてヒーローが活躍するSFサブジ ャンル、物語や演出を優先してリアリティや科学的整合性を無視することが多い)」のなかのさらなる作品群であると思われます。
事実、文学研究者のジェローム ・ウィンターは"Wide-Screen Baroque Revisited"(2016)で次のように書いています。
ブライアン・オールディス は『十億年の宴』(1973年)の中で、E・E・スミス とA・E・ヴァン・ヴォークト がSFというジャンルに与えた影響を論じる際に、「ワイドスクリーン・バロック 」という言葉を初めて使った。オールディスのこのフレーズは、発展するサブジ ャンルとしてのスペース・オペラ の現代的理解に深く絡みついている。言うならば、よく引用されるこのフレーズは、小説や映画のコンベンション(訳者注:ファン大会)やそこでの会話においてのスペースオペラ についての議論に対する、オールディス固有の「ニューウェーブ 」的介入を表しているのだ。 おそらくオールディスは、ウィルソン'ボブ'タッカーが1941年頃にスペースオペラ を "ギーギー鳴っている、悪臭を放つ、時代遅れの、宇宙船ほら話"と酷評したことから、スペースオペラ を救い出そうとしているのかもしれない。(以下のホームページより引用、2021年6月23日閲覧、拙訳、傍線は引用者による)
Wide-Screen Baroque Revisited | UWP
ここでまだ重要な用語が出てきました。「ニュー・ウェーブ」 です。
「ニュー・ウェーブ」とは、1960年代~1970年代に起こった、SF作品に文学的・実験的な要素を入れようとするSF作家・評論家の(主に英語圏 で起こった)運動のことです。 「ワイドスクリーンバロック 」という概念は、この「ニュー・ウェーブ」運動のさなかに遡及的に唱えられたものでした。そもそも、『パラドックス ・メン』の初版(題名は『昨日への飛行』)は1953年に刊行されています。オールディスが序文を書いたのは、いったん絶版になったあと再刊されたものだったのです。オールディスを中心とした「ニュー・ウェーブ」運動の推進者たちが、過去に目を向けた結果「時代遅れだと思われてたスペース・オペラ のなかにも、こんなすごい作品があるぞ!」と『パラドックス ・メン』に代表される作品を持ち上げるために作り出されたカテゴリーが「ワイドスクリーンバロック 」だったというわけです。(〈レンズマン 〉シリーズの第一作刊行は1937年、『非Aの世界』の刊行は1948年、『分解された男』の刊行は1953年で、「ワイドスクリーンバロック 」がはじめて唱えられた1964年から見て一昔前の作品たちでした)
その後、「ワイドスクリーンバロック 」という用語は日本SF界に輸出されて、さまざまな作品を言い表す言葉として使われました。その過程で、オールディスの使用法から、微妙に意味が変容していきます。
クリス・ボイス(1943~1999)の『キャッチワールド』(日本での刊行は1981年)の解説において作家・翻訳家の安田均 さんはこう書いています。
(前略)登場人物はいちおうの性格づけを与えられるものの、ほとんど性格描写はされず、ただ作者の筆に操られるまま巨大なゲームの駒として動いていく。さらに、冒頭第二章、未来の日本の説明にみられるグロテスクな異国情緒(作者は日本の現状をかなり知っていて歪曲した節がある)をはじめとして、さまざまな箇所で見受けられるアクの強さ。ここまで書くと、この作品があるSFのタイプを完全に目標としていることに気がつかれるだろう。
そう、ワイドスクリーンバロック である。(『キャッチワールド』p370より引用)
この文章は「ワイドスクリーンバロック 」という言葉が日本に入ってきたときの印象を記録しています。翻訳版の『十億年の宴』は1980年に刊行されたため、まさに、当時はこの言葉が日本に現れた直後でした。
さらに、安田は作者であるクリス・ボイスを紹介するとき、ある重大な示唆を行いました。
(前略)実質的に認められたのは何といっても本書であり、これで彼(引用者注:クリス・ボイス)は最近のイギリスのSFに顕著な”アイデア 派””観念派”の一員として見られることになった。この派には、他に、バリントン・J・ベイリー 、イアン・ワトスン といったいずれも七〇年代に頭角を現した作家が属す。彼らの作品の特徴となるのは、小説のアイデア 部分に異常なほどの力を注ぎ、つぎつぎにくりだされる(ときには未整理なほどの)アイデア の奔流によって、一種の”めまい”とも呼べる効果を導きだすといった点だろう。これは一方で、マイクル・コニイ、リチャード・カウパー 、クリストファー・プリースト といった小説のスタイルに重点をおく作家群と対置されながら、現在のイギリスSFの活況を担っているといえる。(『キャッチワールド』p371-372より引用)
オールディスのもともとの文章が「舞台の規模」「プロットの精妙さ」「機知、深遠と軽薄の合流」を強調していたのに対して、『キャッチワールド』解説では、「アイデア の奔流によるめまい」が強調されています。
さらに、二つ目の引用文を読むと、クリス・ボイスはイギリスにおける「アイデア 派」に属す作家とされていることがわかります。
この「アイデア 派」とは、70年代のイギリスSF界で起こった作家同士の論争に起因するものでした。このことは、残っている資料があまりなかったので、わたし自身もよく知らないのですが、1976年刊行の『ファウンデーション 誌』にイアン・ワトスン (1943~)とクリストファー・プリースト (1943~)が”Science Fiction: Form versus Content”というタイトルでエッセイを書いているようです。これが発端になったのかもしれません。
Title: Science Fiction: Form versus Content
また、1978年に刊行されたアンソロジー 『アンティシペイション』では、クリストファー・プリースト がイアン・ワトスン を紹介するときに、次のような序文を書いています。
イアン・ワトスン 。わたしとワトスンはしばしばお互いをよき論敵とみなしあっているし(たとえば、この序文でわたしが書いてきたことの大半に彼は同意しないだろう)、創作のアプローチはまったく違っている。にもかかわらず、わたしは彼の作品の多くを高く評価している。(『アンティシペイション』p10より引用、安田均 訳)
1981年に行われたイアン・ワトスン へのインタビューでは、次のように語られています。
ラングフォード(注:インタビュアー):クリス・プリーストとあなたは、SFへのアプローチについて熱い議論を交わしてきました。私らしい粗雑な表現でまとめると、「教訓(教育)Didacticのワトソン」対「美学Aestheticのプリースト」ということになります。"どちらかが先行するのではなく、美学が十分に発揮されれば、いつでも教訓的なものを打ち負かすことができる!」と『ファウンデーション 10』でクリスは言っていました。その段階の議論から5年経った今、あなたには立場がどのように見えますか?
ワトソン:確かに、当時の共同編集者である私たちは、活発な議論をするために始めました。教訓対美学の件は、根底にある政治的な偏見が隠されています。それは、リーズ大会で、SFは運動を支援すべきかどうかという議論の中表面化しました。私の親愛なる誤った友人クリスが、イギリスは占領された国(アメリ カに占領された国)であり、たとえその結果、私たち全員が放射性の塵に吹き飛ばされたとしても、これを変えるために何かをしようとすることはできないし、すべきではないと宣言したのです。これは、自律的であるはずの美的スタンスの破綻です。彼がStatus Quo というバンドを好きなのもうなずけます。
ラングフォード :痛い。後期ハインライン のような教訓的な作家が単なる美学者の左に位置していることを示唆しているのではなく、哀れな老クリスに対するただの悪口であることを願っています....
(Ian Watson Interview (1981) より引用、2021年6月23日閲覧、拙訳)
面白いことに、本来は直接関係なかったはずのワトスン対プリースト論争と、「ワイドスクリーンバロック 」が、日本においては関連づけられて語られるようになったのです。
それにより、本来ワイドスクリーンバロック の母体であったはずのニューウェーブ 運動と切り離されて考えられるようにもなりました(ワトスンはニューウェーブ 運動に批判的でもありました)。
こうして、日本SF界においては「ワイドスクリーンバロック 」の中核に「アイデア の奔流」を置く理解が広まりました。
そして、その代表作家として目されたのが、イギリスのSF作家、バリントン・J・ベイリー (1937~2008)です。
1983年に日本で翻訳版が刊行されたバリントン・J・ベイリー の『カエアンの聖衣』の解説で、SF評論家・翻訳家の大野万紀 さんは次のように書いています。
(前略)科学用語や擬似科学 的論理は山ほど出てくるのだが、ハードSFとは違い、よく読めば矛盾がいっぱいだ。ところが読んでいる間、こういったことはまったく気にならない。デタラメだろうがインチキだろうが、ひどくぬけぬけと語られ、しかも物語の中ではそれで当然だと思えてくるから不思議だ。
こういう種類のSFを、ふつう〝ワイドスクリーン・バロック 〝と呼ぶ。ブライアン・オールディス が『十億年の宴』で使ったことばだが、スペース・オペラ の奔放さと雄大 さを受け継ぎつつ、観念性と軽薄さを同時に武器とするような離れ業をみせる。ひとつひとつじっくりと味わう間もないほど、これでもかこれでもかと詰め込まれたアイデア の、めまいを起こしそうな密度の濃さ。それを柔らげるコミカルなユーモア感覚と、どこまでも広がっていく気の遠くなりそうなスケールの大きさ。無限の時間と空間。個々の人間ではなく、文明や種族のレベルで語られる観念的な物語。何重にも入り組んだプロット。めくるめくセンス・オブ・ワンダー 。こういったすべてをひっくるめて、意識の拡大という、SFの重要な特質が効果を発揮するのだ。ハードSFが論理(ロジック)に重点を置き、文学的SFが文体(スタイル)に重点を置くところを、ワイドスクリーン・バロック は観念(アイデア )に重点を置くのである。 そして、それこそが、最もSFらしいSFであり、SFファンが最も魅惑的だと感じる形式――そしてSFファン以外の読者にとまどいを感じさせる形式――であると断定しても、おそらく間違ってはいないだろう。(「カエアンの聖衣」解説 より引用、傍線は引用者による、2021年6月23日閲覧)
この解説でも、ワイドスクリーンバロック の特徴が「アイデア 」にあるとされています。
このように、バリントン・J・ベイリー がワイドスクリーンバロック の中核的作家とされるのは、おそらく日本SF界においての独特な見解でしょう。
たとえば、Science Fiction EncyclopediaのWidescreen Baroqueの項目には、ベイリーは載っていません。むしろ、イアン・バンクス やスティーヴン・バクスター 、ジョン・C・ライトなどの「ニュースペースオペラ (科学的知識や説得力のあるテクノロ ジー に基礎を置き、遠未来を舞台にし、よりリアリティを追及したスペースオペラ 。1990年代~2000年代にかけて多くの作品が書かれる)」に分類される作家たちが入っています。(日本SF作家の大原まり子 さんも掲載されています)
Themes : Widescreen Baroque : SFE : Science Fiction Encyclopedia
(2021年6月23日閲覧)
※ベイリーの小説は、現在では電子版もあり、かなり手に入りやすくなっています。(以下電子版がある作品)
バリントン・J・ベイリー を中核作家に置き、「アイデア の奔流」「アイデア によるめまい」を特徴にするという、日本SF界にて独特の把握をされた「派生的ワイドスクリーンバロック 」は、やがて、独自の影響力を持ち始めます。
そのような「ワイドスクリーンバロック 」にもっとも大きな影響を受けた一人として、劇作家・脚本家の中島かずき さんが挙げられるでしょう。
新訳版の『カエアンの聖衣』の解説にて、中島さんは次のように書いています。
それまでモヤモヤとしていたやりたいことが、ワイドスクリーン・バロック に出会って「これだよ、おれのやりたいのはこういうことなんだ」とイメージできたのだ。中核になるアイデア を軸に、まわりに付帯的なアイデア をちりばめためまいがするような大法螺話。舞台なのでなかなか宇宙的なスケールまではいけないが、自分なりにワイドスクリーン・バロック 的手法で書いていこう。SFとしての定義は違うのはわかっているが、作劇術としてのワイドスクリーン・バロック 。それをやっていこう。(『カエアンの聖衣〔新訳版〕』、電子版より引用)
こうして、作られたのが、アニメ「天元突破グレンラガン 」(2007)と「キルラキル 」(2013)でした(「キルラキル 」は『カエアンの聖衣』の直接的影響があります)。
『天元突破グレンラガン 』で、今石洋之 監督の「ドリルをテーマに26話のアニメがやりたい」という無茶ぶりに「ドリル=螺旋力」と読み替えて、一人の男の成長と、生命の進化と宇宙創成の二つをテーマに描くと決めたとき「これで本気でワイドスクリーン・バロック がやれる」と一人ほくそ笑んだものだ。(『カエアンの聖衣〔新訳版〕』電子版より引用)
打ち合わせのなかで「女子高生が特殊な能力を持つ制服を着て戦う」というアイデア で落ち着きそうになった時、これはもう『カエアンの聖衣』は避けられないと腹をくくった。(『カエアンの聖衣〔新訳版〕』電子版より引用)
また、わたくし(草野原々)もバリントン・J・ベイリー 型のワイドスクリーンバロック に影響を受けた一人です。
短編集『最後にして最初のアイドル』収録の「暗黒声優」は、どんどん規模が巨大化するスペースオペラ でもありますので、オールディス型のオリジナル・ワイドスクリーンバロック にも適合する作品でしょう。
そのほかにも、長編の前後編となる『大進化どうぶつデスゲーム』と『大絶滅恐竜タイムウォーズ』もベイリー型ワイドスクリーンバロック の影響下にあります。(特に後編の『タイムウォーズ』のほうは、アイデア の奔流を作り出すことを意識しました)
『レヴュースタァライト 』に「ワイドスクリーンバロック 」をもじった「ワイルドスクリーンバロック 」という言葉が使われているのは、もともとのオールディスから、ベイリーへ、そして中島かずき さんへという系譜が背景があると思われます。
では、ひるがえって、『劇場版少女歌劇レヴュースタァライト 』はワイドスクリーンバロック なのでしょうか?
オールディスが唱えたオリジナルの意味合いのワイドスクリーンバロック とはいえないでしょう。 『レヴュースタァライト 』はスペースオペラ ではなく、舞台も太陽系サイズではありません。
しかし、ベイリーを中核とした、「アイデア の奔流とめまい」によって特徴づけられる、派生的意味でのワイドスクリーンバロック としては合致するといえそうです。
さらには、中島かずき さんの言う「作劇術としてのワイドスクリーンバロック 」として、大きくあてはまりそうです。
そしてなにより、『劇場版少女歌劇レヴュースタァライト 』は、ワイドスクリーンバロック の母体となったニューウェーブ 運動の精神と共鳴しているでしょう。 ニューウェーブ 運動の提唱者である、J・G・バラード (1930~2009)はエッセイ「内宇宙への道はどちらか?」で、追及するべきなのは外宇宙ではなく内宇宙であるとしました(原文手元にないので引用できません。すいません……)。登場人物の精神を詩的映像でひたすら描いていく『劇場版少女歌劇レヴュースタァライト 』はまさにここにあてはまるものといえるでしょう(バラードは時系列を破壊する作品や砂漠の描写をよく書いていた点も似ています)。
www.tsogen.co.jp
VIDEO www.youtube.com
VIDEO www.youtube.com
「正解するカド 」:上位次元人とのファーストコンタクトという近年のアニメでは珍しいテーマを扱っているSFアニメ。中盤からの脱線的超展開と、終盤にかけての規模の拡大および強引すぎる身も蓋もない終わらせ方は、ヴァン=ヴォークト 的な古典的ワイドスクリーンバロック を彷彿とさせる。
VIDEO www.youtube.com
「ゲキドル」:『劇場版レヴュースタァライト 』と平行して見るべき作品。奇しくも『劇場版』と同じ2021年に放送された。こちらも、演劇をテーマとしているが、レヴュスタとはまた違う視野から描いている。
エピソードが進展するにつれて指数関数的なスケールの拡大を経て、最終話ではとんでもないところにつれてかれる、まさに「めまい」を起こすワイドスクリーンバロック 。













![SFマガジン 2023年 10 月号 [雑誌] SFマガジン 2023年 10 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51TfOmNCXGL._SL500_.jpg)